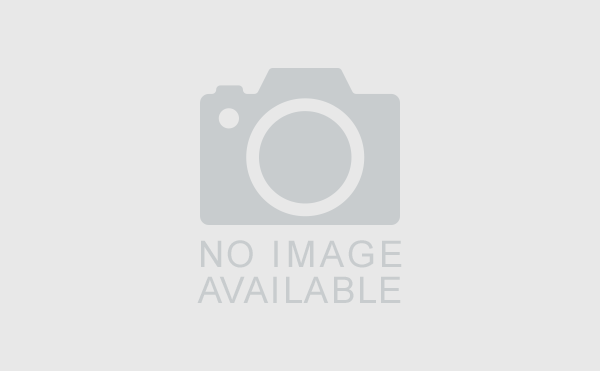【Wonkish】「分散」という欺瞞。巧妙なレトリックにだまされてはいけない
最近よく見かけるミスリードの例
前置きが異常に長くなったが、本題に移ろう。
最近、いわゆる識者やプロと呼ばれる人たちが「分散」という言葉を巧妙に使い、聴衆をミスリードしている。
ここではいくつか例を挙げる:
1.「オルカンは米国の比率が大きすぎるから、米国以外への投資と組み合わせ分散するべきだ。」
2.「S&P 500指数は加重平均指数で偏りがあるから、より分散状態のよい単純平均指数に投資すべきだ。」
3.「時間的分散を実現できる積立投資(ドルコスト法)は有効だ。」
いずれも言いたいことはわかるし、結論が間違いだとは言わない。
しかし、ここに「分散」という言葉を用いると、その正当性がかなり怪しくなってくる。
1. 「オルカンをさらに分散せよ」
オルカンは、株式市場だけで言えば、相当に広範な資産を取り込んだ株価指数、またはそれをトレースするファンド群だ。
オルカンはマーケット・ポートフォリオの近似としてかなり優秀な部類に入ると考えてよい。
これに米国以外への投資を加えても、分散状態が向上するわけではない。
この主張の背景にあるのは、米国株が高すぎるとの仮定であろう。
つまり、この主張の真意とはリスク分散ではなく、リターンにかかわるものなのである。
米国株は下方リスクが大きくなっているようだから、リターンが下ブレしないように他のものを入れなさいということだ。
前提は、米国株の下方リスクが高くなっているとの認識だが、効率的市場仮説から言えば、この認識が正しい確率は半々だろう。
2.「S&P 500加重平均は分散がよくない」
最近マグニフィセント7など大型グロース株またはテック株が調整している。
しかし、それでもMag7はS&P 500の時価総額の30%を占める。
指数計算上に偏りがあるのは間違いない。
しかし、偏りがあっても分散が悪いことを意味しない。
米市場の近似として考える場合、どんなにMag7への偏りがあっても、加重平均指数の方が単純平均指数よりよい近似だ。
より低いσリスクを提供してくれる。
この主張でも、真意は分散ではなく、ファクターごとのリターン予想の違いにある。
つまり、リスク分散ではなくリターンの議論になっている。
前提はMag7等からそれ以外へのローテーションが起こるとの読みだが、これも効率的市場仮説から言えば正しい確率は半々だろう。
(次ページ: ドルコスト法は時間的分散なのか??)