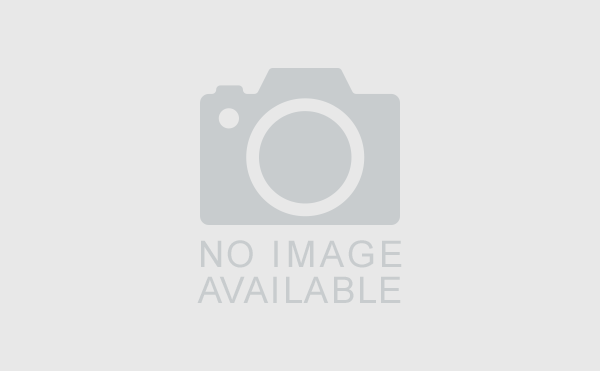【Wonkish】「分散」という欺瞞。巧妙なレトリックにだまされてはいけない
3.「ドルコスト法は時間的分散になる」
これは間違いではないが、ミスリードだと思う。
そもそも本来の「時間的分散」の意味は何か、ざっくり説明しよう。
ある投資の1年のボラティリティをσとする。
n年投資した場合、σ×√n となる。
1年あたりなら σ÷√n だ。
nが長くなるほど年あたりの数字は小さくなる。
これが本来の「時間的分散」の意味だと思う。
しかし、この言葉が異なる意味にも使われている。
ドルコスト法の拠出のしかたを「時間的分散」と呼ぶ人がいる。
これは間違いではなかろうが、首を捻りたくなる。
ドルコスト法の拠出のしかた自体を「分散」と表現すべきか。
正確には「平準化」なのではないか。
ドルコスト法で拠出しても、1本1本の投資分が分散されるかどうかは、取り崩しまでの投資期間による。
タイミングを変えることを投資分散と呼ぶのが厳密なのか、筆者は疑問視している。
ましてや、ドルコスト法は下げ相場の時に有効だ、などというレトリックは全く当てにならない。
効率的市場仮説から言えば、将来が下げ相場になるか上げ相場になるかは予見できないからだ。
この議論なども、結局は隠れた不適切な前提によるものであり、それはリスク分散というよりはリターンにかかわるものである。
筆者はドルコスト法については極めて否定的だ。
制度上それが強制されている場合(積立NISA、iDeCo、持株会など)を除けば鼻にもかけない。
長期投資家が狭義の「時間的分散」を図る場合、投資時期を毎月に(あるいは毎年でも)分散したからと言って大したことではない。
投資の期待リターンとは、投資金額×投資期間によって決まる。
ドルコスト法はその式にはあまり関係してこない。
ドルコスト法では多少エントリー価格が平準化するだろうが、長期投資家は別に狭義の「時間的分散」を実現できているので、大した差にはならない。
ドルコスト法に意義があるとすれば、行動ファイナンス的な観点だ。
第一に投資を習慣化・自動化できる。
第二にエントリー時期と価格についてあれこれ考える必要がなく、後でくよくよする必要もない。
これらのメリットは投資のキャリアを積むにつれ、急激に軽微なものになっていく。
(次ページ: 「分散」というレトリックの罪)